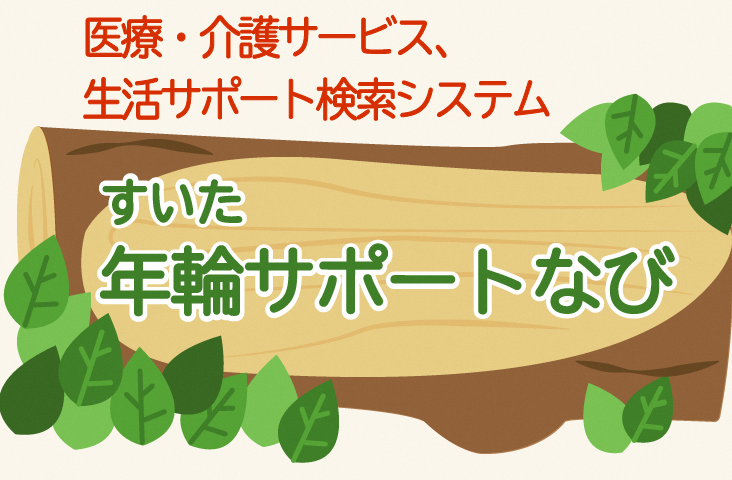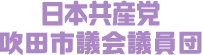■戦後80年の取り組みについて
問)今年は戦後80年。吹田市でも、市役所ロビーの展示、メイシアターの展示、平和祈念資料館等で平和の取り組みが行われている。平和祈念資料館では『きけわだつみのこえ』の展示や佐井寺出身の方の展示などひきこまれるものだった。見学したこどもたちも、戦争をなくすためには?ということに対し『けんかをしないように』『いつもたのしくすごす』と書いていて、努力がわかるもの。「吹チューブ」も、吹田市の戦争の跡をとし、高浜神社の前の道路が建物疎開の跡であることなど紹介を。建物疎開による疎開道路は商店街の方にもつながっていることや、吹田駅の駅舎の柱が当時の木製のまま残っていること、爆撃があったとされる場所が駅前にあること、吹田操車場が軍需物資輸送の拠点となり、交通路として使われていたことや防空壕が残っているお寺、金属回収令でいったん拠出した梵鐘。全国で80%以上が失われたのに、戦後に元のお寺に戻ってきた梵鐘など、吹田市にはもっと戦争の跡の記録があるが、今年の取り組みを深堀し、保存し記録に残してはどうか。
(答:市民部長)取り組みの集約を行い「戦後 80年事業の取り組み」として市ホームページで公開する形で残していきたい。今回「吹チューブ」で取り上げていない戦争の記録は実態調査を含め、保存のあり方を検討していく。
(問)戦前、天皇制政治のもとで主権在民を主張し、侵略戦争に反対したために、治安維持法で弾圧され、多くの国民が犠牲になった。治安維持法が制定された1925年から廃止されるまでの20年間で、強制的に連行し拘束された人は数十万人、検挙者は6万8274人、拷問による虐殺93人、獄死128人をはじめ、弾圧が原因で命を落とした人は500人を超えた。日常的な監視、予防拘束・拘禁など人権を蹂躙し、狂暴な弾圧が荒れ狂った。無数の人を弾圧し自由を奪った稀代の悪法が治安維持法。
戦後、当然この法律は廃止。この悪法と同様の法律をつくろうとする動きや、外国人が日本で日本の制度の下で過ごしていることが治安そのものを悪くしているとSNSなどで発信がある。各県の知事からも、根も葉もないデマを流し外国人を攻撃するやり方への批判や懸念し、7月24日、「争いよりも対話、異なる意見を尊重し、困難な時こそ温かい心で、困難な時こそ誰1人置き去りにしない」とし「事実に基づかない情報が広まっていることから、民主政治を脅かす不確かで根拠のない情報から国民を守り、国民が正しい情報に基づいて政治に参画できるシステムの構築を求めていく」と全国知事会で青森宣言が採択された。
人間にはファーストもセカンドもない。すべての人にとって良い社会を築くことを目指す、差別も分断もないことをすすめることだ。吹田市の第4次総合計画には「市民一人ひとりの人権が尊重され、だれもが対等な社会の構成員として平和に安心して暮らせるまち」と目標にある。その目標を持つ吹田市の市長として、中核市市長会でも全国知事会のように意思表明の働きかけを。排外主義について市長の考えを。
(答:市長)人の命、民族、国家、国民、文化などにファースト、セカンドと順位付けを行う社会を望まない。排他的な考え、差別が紛争のバックグランドとなってきた。その反省から平和を希求する民主国家の道を歩んできた。この理念を正面から否定する動きがネット上で攻撃性を増していることを懸念している。全国の首長が集まり議論する場があるが、みなさんが同じ感覚でいる。今後も連携し民主的な地方政治を守っていく。
■ファミリーシップ制度創設を
(問)パートナーシップ宣誓制度がスタートし2年となる。積極的な取り組みを推進するため、民間団体と自治体が協力して取り組む「わたしたちだって、いいふうふになりたい展」の開催や、パートナーシップ宣誓証明を受けた2人とその子や親等を「家族」として宣誓対象とするファミリーシップ制度を設け、多様な家族の在り方を尊重する制度に拡充してはどうか。市長の考えを聞く。
(答:市民部長)人権を尊重する社会の構築を目指した取組みの一つとして、ファミリーシップ制度の導入に向けて、国や他の自治体の動向を注視している。引き続き、パートナーシップ制度の宣誓を行われた方々をはじめ、関係する皆様からの御意見をお伺いしながら検討する。また、提案の展示について前向きに対応を進めたい。
(答:市長)多様な市民、それぞれの人権を尊重する社会の構築につとめる。
■子ども誰でも通園制度について
(問)保育園やこども園に通っていない0歳から満3歳のこどもたちの育ちを応援し、保護者の孤立した育児の中での不安を解消するため月に10時間まで利用でき、都道府県を超えた広域利用が可能になる。全国どこでもアプリで空き状況を調べ、直前でも予約ができるシステムをつくる。事業を行う施設は保育者の半分は無資格でよく、空き定受け入れた分だけ報酬が払われる出来高払い制。2026年4月実施としているが、今のままスタートさせるには無理がある。慣らし保育もなく、子どもにストレスを与え、実施する施設にも大きな負担。①一時預かり事業とあわせて公立保育園や、のびのび子育てプラザで実施し、民間事業者の実施とあわせて基幹的な役割を公立が果たせるようにすること。②人見知りの時期の乳幼児を、事前面談もなく単発的に数時間預けることは、子どもにとって大きなストレスになり、保育事故が起きる危険もあるので対面による面談は必須にするなど吹田市独自の安全基準を設けること。在園児もこども誰でも通園制度の利用もどちらも守られるよう、市独自の安全基準や方針を示し、必要な予算をあわせて示すべき。
(答:児童部長)市としても手厚い保育体制が望ましいと考えている。国に準拠することを基本にし、利用前の面談の工夫や初期段階には親子通園の活用など、類似する保育事業も参考に検討したい。
■「手話は言語」のアピールを
(問)国際手話が公用語の国際スポーツ大会「デフリンピック」が11月に東京で開催される。関係者の30年来の悲願が実った初の日本開催。70~80カ国・地域、約3000人の選手が集う。選手の多くが働きながら遠征費も自己負担。パラリンピアンが受けられる支援もデフアスリートにはない。パラリンピックの認知度が93%、デフリンピックは15%。吹田事業所にも参加する代表選手がいる。9月23日『手話言語の日』職員のみなさんが「手話であいさつはできるようになろう」とバッチをつけ、実際に挨拶し努力されている。デフリンピック応援のアピールや、「手話言語の日」ブルーライトアップなどできることがあるのでは。
(答:福祉部長)9月23日の手話言語の国際デーに合わせ「手話が言語である」ことへの認知を広めるため、本年9月23日から26日まで、本庁舎西玄関、メイシアター館名灯のブルーライトアップを実施。デフリンピックは、市のイメージキャラクターすいたんを大会の公式な応援隊の申請中。今後は、大会エンブレムを身につけたり、SNSで情報発信していく。
■補聴器購入助成制度について
(問)聞こえにくくなるとコミュニケーションが円滑にいかなくなり、自分の気持ちをうまく伝えられない等ストレスを感じることも増える。自信をなくし、社会的に孤立し、うつ状態に陥いるなど、社会生活に悪影響を及ぼす可能性もある。危険を察知する能力が低下し、車が近づいてきても気が付かず、交通事故などのリスクが高くなる。最近は、難聴により認知症の発症リスクが高くなることが報告されている。聞こえにくさは、本人や周りの人、家族にとっても生活の大きな支障となる。加齢性難聴の方の生活を改善するうえで、非常に有効な手段。全国 471の自治体で、大阪府内19の自治体で取り組まれている。国に要望するだけでなく、独自で支える仕組みについて早急な検討が必要。
(答:福祉部長)居住地域によって格差のない補聴器購入費用への補助制度を創設するよう、国や府に要望している。加齢性難聴の早期受診の必要性や、補聴器を適切に使用することについての啓発を継続し、先行して取組を開始している市町村の実施状況等について注視していく。
*その他、物価高騰から市民の生活を支える対策、熱中症対策、福祉人材確保、吹田駅前の再々開発について質問しました。