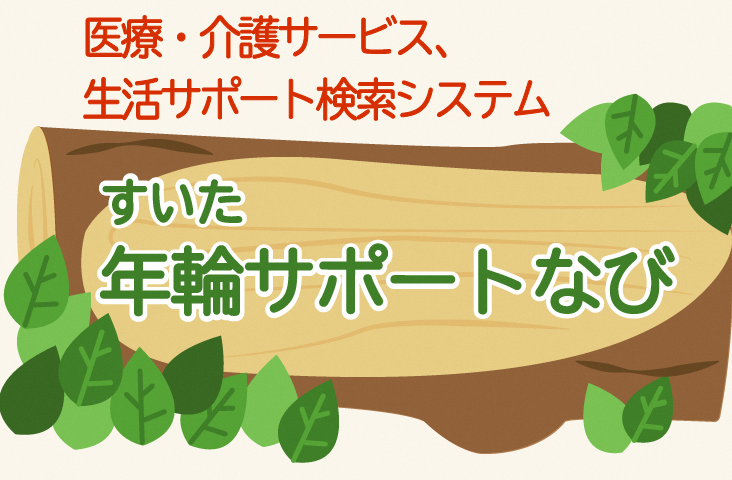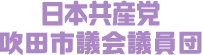2025年度は、低所得層への軽減が国の改正により一定軽減される世帯が新たに約180世帯増えます。 保険料については、限度額の引き上げ(104万円から106万円)はあるものの、保険料は中間層・低所得層含め、軽減または保険料は据え置きとなります。 昨年度より一般会計の繰り入れは増えているものの、これは国の改正による保険料軽減の分により、繰入をおこなわれるものです。 保険料の決め方や大阪府の方針には問題があると考えています。
2025年度は保険料が統一化され2年目です。 2018年から暫定期間も含めると6年が経過しました。 この間の保険料ですが、2017年、統一化に向けてスタートする前とくらべてみると、30代夫婦と就学児2人、年収300万円の4人世帯で2017年には年間31万8110円だった保険料が、2025年度は37万6819円、5万8709円、値上がりしています。 とくに2024年度は府内全市町村で値上げとなり、全国で1番高くなった国保料が、2025年度は下がったとはいえ、若干の引き下げであり「高すぎる」ことに変わりはありません。 今回の若干の引き下げは、府国保会計剰余金約132億円の半分を取り崩す中で、引きさげになったようですが「剰余金」は 2023年度までのもので、2024年度の多く取りすぎた給付費減分は含まれていません。 府内統一化の保険料は高すぎる」上に「取られすぎている」ということです。 あまりの高さに2023年度単年度赤字になった自治体が37自治体に上りました。 理由は「収納率が下がり保険料が集めきれなかった」「保険者努力支援金が先取りされて納付金計算のときに入れられてしまったため」「被保険者数が予想以上に減った」ことなどがあげられています。 大阪府の納付計算そのものが正しいか疑問の声が各自治体からも上がっています。
統一化になり、保険料について府の方針に基づきがんじがらめになっているようにみえますが、統一保険料としている都道府県では大阪府と奈良県のみで、それ以外の都道府県では市の独自の保険料を認めています。 国は市独自で実施する市民への健康施策、保険料軽減策に補助することを違法とはしていませんし、技術的助言に法的拘束力はなく、市民の暮らしを守る地方自治体としての役割を大阪府に認めるよう言い続けてください。
保険料の収納率については大阪府が市町村の目標を設定し、目標を達成すればペナルティーはありませんが(吹田市は達成している)目標の収納率に届かなければ府への納付金を上乗せする仕組みとなっています。 市の黒字分や基金がなくなれば、かかる費用などについては市町村で何とかして支払いなさいという仕組みにしています。
大阪府は、統一保険料として保険料は強制しながら納付が少ないときには市町村の責任にして、市町村の保険加入者に保険料を上乗せするという身勝手な仕組みにしています。 大阪府の身勝手で理不尽な仕組みをあらため、府が補填する仕組みをつくり暮らしを応援するよう、大阪府に府内の市町村と協力して求めていただくよう求めます。
人間ドックの補助に加え、脳ドックの実施など取り組みを進めておられます。 保険料の減免などにあてる分の一般会計からの繰り入れは、新年度ゼロになっており、この間の予測は大阪府が目標設定したよりも収納率が上がり単年度黒字となっています。 こどもの均等割りの部分を国が行っていない範囲を、こども医療費と同様まで広げることや、保険料の軽減につながる、他市事例にもある「健康増進支援金」という給付する型の支援策などの取り組みを、物価高騰で生活が厳しくなっている市民の暮らしの立場に立った対応を市独自で実施されるように求めます。
新年度の保険料について、限度額の引き上げについて、議案参考資料にはそれぞれの額はあるものの、合計額についてはどこにも記載されていません。 また新年度の予算の資料に保険料が示されている資料はなく、運営協議会にも示されていません。 理由がなにかは不明ですが、昨年度までは、その資料が示されていました。 新年度の予算の審査をするにあたり、保険料は暮らしに関わる問題ですから、資料はきちんと示すべきです。
昨年度より、窓口の一部が民間委託され、市の職員の数は減っおります。 委託職員の人数が多くなっていますが、相談をしにくい窓口となっていないか、今後きちんと検証し、相談のしやすい窓口となるようにすることが必要だと思います。 以上を申し上げ意見とします。
(全会一致で可決)