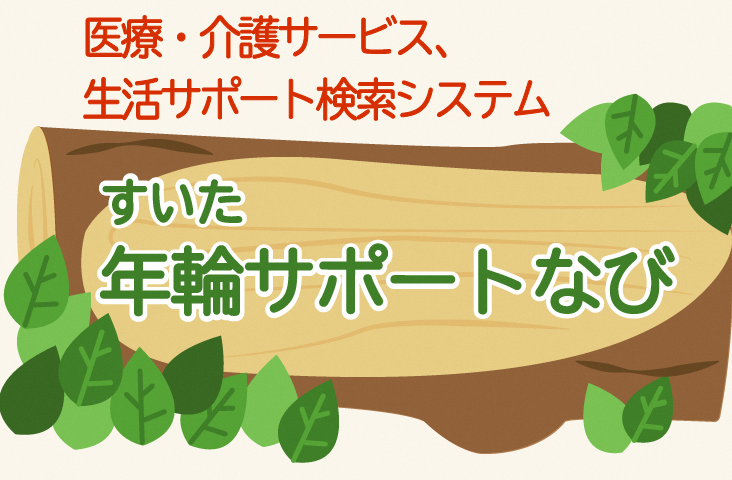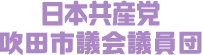※3月24日に行われた、定例会最終日で述べた日本共産党の意見を紹介します。
評価できる点
1.消防職員特殊勤務手当の変更について
(そのほとんどが1975年以来の見直し)火災や救急等で現場へ緊急出動した際の消防業務従事手当及び被災地への緊急消防援助隊派遣手当が新設されたことは評価できます。ただ危険を伴う業務であり、提案された金額が妥当なのか、さらに実態に見合った引き上げを検討されたい。
2.救急隊の増隊について
救急隊10隊に増隊後、現地到着まで2023度年7分29秒であったものが2024年度は7分9秒に短縮されています。高齢化により、さらに救急の需要は増える傾向にあり、♯(シャープ)7119の利用を周知し、緊急を要する人に1秒でも早く対応できるよう、引き続き努められたい。
3.消防における女性職員の働き方について
2024年度から女性管理職1名(主幹)を配置し、女性活躍及びジェンダー平等の視点で研修や施設整備等、取り組みが進められていることは評価できます。来年度4名の女性職員が入職予定とされ、いっそうハード面、ソフト面ともに女性職員が働きやすい環境整備に努められたい。
4.危機管理センターについて
見学時に、避難所や災害状況を疑似体験できる啓発コンテンツの制作、また衛星通信機器の導入等、災害に備えた関連予算については評価できます。災害対策として循環型トイレを試行的に実施することは評価できます。効果の検証を確実に実施し、導入につなげられたい。また国に対し、補助金の継続を求めてください。また水を使わず便袋を自動熱圧着後、自動送りで排泄物を一回ごとに密封し廃棄できる災害用トイレについては順次増やすことを求めます。
5.市長のタウンミーティングについて
年3、4回実施する予定で、人数などの要件が合えば対象は限定していないとのことであります。市長自身が直接市民と対話し、各分野の市民の実態を把握し、意見を反映した施策を進めるために広く周知することを求めます。
6.半年間小学校給食の無償化について
行うことは評価できます。今後、国の動向を把握しつつ、残り半年も継続実施するよう前向きに検討されたい。
7.戦後80周年の取り組みについて
市民と連携し実施することは評価できます。個人や市民団体が保有する吹田の戦争の歴史資料を市として保存する手法を検討していただきたい。
8.学童保育の設備の修繕等について
新年度ですべての学級のエアコン改善が終了する予定です。トイレや壊れた備品の交換等、放課後の子どもの生活の場にふさわしい水準を維持していただきたい。
9.福祉事業者への応援金について
物価高騰に係る福祉施設等への応援金支給については市民生活を支える重要な社会インフラである福祉施設等の運営支援となるため、引き続きの実施は評価できます。
10.手話講座の充実について
入門講座の定員を増やすこと、またステップアップ講座の創設は入門コース、会話コースから続く講座で、途切れることのなく、奉仕員の養成や手話通訳者の養成につながります。日常会話のなかでコミュニケーションの手段として取り組みを進めることにつながり、評価できます。
11.上の川周辺整備事業について
上ノ川橋から蓮華寺橋までの300m区間の遊歩道上面整備の設計であり、アンケート結果等、市民意見の反映と説明を十分に実施しながら進めること。また、蓮華寺橋から花壇踏切までの遊歩道を延伸する350mの区間は、市独自で進める工事となり、府や国への一層の働きかけと協力要請に努められたい。
12.総合自転車対策事業におけるJR吹田駅前北自転車駐車場大規模改修工事について
JR吹田駅北側の駐輪場が足りておらず、JR吹田駅前北自転車駐車場の大規模改修の早期実施を求めてきたことであり評価できます。一時利用、定期利用の利用率を勘案し、定期利用のみとなっている現状の再検討を求めます。
13.吹田市居宅支援協議会へ予算増額について
600万円の予算が増額されたことは評価できます。困っている人に届くよう、更なる制度の周知を図り、重層的支援体制の中にも位置づけて制度利用へと繋げ、必要に応じて事業を更に拡充することを求めます。
要望・改善が必要な点
1.消防女性職員の生理休暇について
働きやすい環境整備は進められているが、職員7名全員の生理休暇取得状況は、2023年度2回、2024年度10回と、ほとんど休めていない。生理中に重労働で危険を伴う現場での勤務は過酷である。生理休暇が取得できる体制整備を求めます。
2.職員の給与改定について
国家公務員の給与改定に準じ、職員給与の大幅引き上げがされます。特に初任給等、若年層に重点をおいた改定は人材確保につながることを期待したい。質疑の中で、地域手当が16%に引きあがると想定される2年後に、豊中市との初任給の差は約2千円になるとのことですが、地域手当16%は流動的であり、北摂他市に比べてもそもそも8号給低い給料体系を改めることを求めます。また消防職員の給与は、一番高い豊中市と比べ、大卒初任給で3万円、高卒で2万円の格差があり、早期の改善を求めます。
3.基幹20業務の標準化に対応するシステム構築について
現在も進められていますが、その移行経費は、2021年度から2024年度まで約17億円、2025年度歳出約10億円、合計で約27億円の市の持ち出しです。移行経費については、国が全額補助することになっていますが、そうはなっていません。また、運用経費についても、3割削減を目指すと閣議決定されているが、全国の中核市の調査で、経費は1.2~3倍の費用増大が見込まれており、中核市市長会で引き続き国に強く求めていただきたい。また、標準化により、市独自の事業については、カスタマイズする必要があるが継続するよう求めます。
4.手話言語条例施策推進方針に基づく対応について
各部署ばらつきがみられます。庁内の情報共有をはかり、先進的な取り組み事例を参考に各部で施策を充実することを求めます。
5.市民センターや公園等、市の公共施設のトイレについて
バリアフリー化とともに、安全や個人の尊厳が守られる仕様となっていないところは、早急に改善を求めます。
6.男女共同参画センターについて
現在、部屋の収容可能人数の関係で人気の講座は希望者全員が受講できない場合があります。研修や啓発、市民活動の交流促進といったセンターの事業目的を達成する観点から、老朽化対応という消極的な修繕ではなく、より使いやすい施設となるよう設計されたい。また、2027年度から3階に資産経営室が移転する予定だが、市民の利用に供する施設とすることが望ましいと考えます。北千里駅前再開発の進行状況を把握し、移転先を再考するよう求めます。
7.都市魅力発信事業について
EXPOCITYでスプラッシュパーティを予定しています。単なる水かけイベントではなく、真面目な企画では来てもらえない子育て世帯へのアウトリーチが狙いとの趣旨は一定理解しますが、広場の使用料が高いため実施場所の変更を検討されたい。
8.健都イノベーションパークにおける中学校の給食センター整備について
2025年3月に事業者を募集し夏ごろに事業者が決定するとしています。給食提供に十分な経験と能力をもった事業者を選定されるよう求めます。
9.不登校支援について
現在、あるくの森では施設の受け入れ可能人数や支援体制により1日の最大人数は100名となっています。新年度は児童センターでの実施や校内支援教室の設置を増やす等、受け入れ場所を拡大するが、いっそうの拡充が必要であり、あるくの森の第二の拠点についても検討されたい。
10.教員働き方改革について
月80時間以上の残業をなくす取り組みをすすめようとしています。自動採点システム、学校副管理者の配置増など、教員を増やす以外の取り組みは行われようとしているが、市費専科講師の配置が少なすぎます。効果検証をするというが、部活動の委託のようにスピーディに拡大するよう求めます。
11.学童保育指導員確保について
新年度には民間委託が4か所拡大し、合計で20か所にもなるが依然として指導員の不足は解消されない。2年前の市長選挙で後藤市長が言及していた指導員の正規職員化も含めた検討が進んでいない。抜本的な対策をとることを求めます。
12.二十歳を祝う式典について
市立吹田サッカースタジアムに会場を移してから式典費用が高騰している。二十歳の若者を励ますという式典本来の趣旨に立ち返るよう求めます。
13.感染症対策について
コロナが5類となったが、福祉施設では感染の拡大などもたびたびおこっています。相談や必要な支援はいつでもうけられるようにすることとあわせて、コロナ後遺症で悩んでいる方の相談を受け、必要な医療につながるように支援の体制を確保されるよう求めます。
14.こども発達支援センターについて
新たに5歳の発達相談や巡回相談の拡充など、こどもたちの支援の充実が予定されています。専門職の配置が増員されるが、新たな事業だけでなく、これまで築いてきた早期発見早期療育のシステムを基本に、専門職の欠員が出ることがないよう、充分な専門職の体制でこどもたちの発達が保障されるよう求めます。
15.児童センターについて
新年度から中学生までに年齢拡大されます。また日の出児童センターは高校生までの受け入れ拡大と不登校の受け入れが新たにスタートします。教育支援教室との研修など実施がされてきているが、新しい事業にふさわしい体制とするため、直営の児童センターは児童厚生員の欠員の解消、また指定管理の施設にも十分な人員の配置ができるよう求められたい。
16.生活困難者への重層的支援について
計画に基づき、事業が行われていくが具体的な予算としては情報の共有のみとなっています。特に困難事例の受け止めは、地域包括支援センターや障がい者相談支援センター、子育て広場や地域ごとに配置されている社会福祉協議会のCSWとなるが、そのための人の配置はなく、計画が着実に実行できるのか疑問です。多機関協働を担うとしている福祉総務室にも人員の配置はありません。各室課に受け止め隊を配置とのことだが、今後、居住支援協議会との連携や困難女性支援の担当との連携など、必要な専門職の配置と困難な方に支援が届く体制づくりで計画倒れにならないよう求めます。
17.「吹田市公共交通維持・改善計画」の中間見直しに係る検討業務について
地域コミュニティ交通の創出について、地域コミュニティ交通導入ガイドラインが策定されたが、導入意向を示す団体・事業者は無く、ガイドラインは未活用のままとのこと。公共交通空白地域、困難地域の解消、高齢者や障がい者、妊産婦の方等、誰もがお出かけしやすい交通支援の再検討を、計画見直しで反映させることを求めます。
問題点
1.物価高騰対策予算
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金約6億円と市の予算約2億6千万円を使って、小学校給食費無償化及び中学校給食半額補助、福祉施設の応援金の事業を実施するが、中小業者や幅広い市民への支援がないことは大変残念です。
財政調整基金は、2025年度当初残高は約84億6千万円だが、決算後の当初残高は約124億6千万円になると予測されています。財政調整基金は災害やいざという時のために積み立てているものであり、物価高騰対策に財政調整基金を積極的に活用し、市民生活を守るべきだが予算内容は極めて不十分です。単に一時的な給付ではなく、たとえば就学援助金の対象を生保基準の1.2から1.3倍に引き上げることや国保料、介護保険料を引き下げるなど、家計の支出を減らして、実質的に市民生活を支えるような施策の実施をすべきです。
2.大阪関西万博に対する予算
関心は依然低いままです。4月に開幕すれば、自ずと行きたいという市民も増えることが予想されるとはいえ、実施主体ではない吹田市で、万博のため職員を増員されていることに市民理解は得られません。フラワーカーペットやワークショップなどの取り組みも、内容を否定しているのではなく多額の税金を投入することの是非が問われます。
3.高等学校等学習支援金の廃止
市は、現在物価は上昇しているという認識でありながら、国・府の制度拡充により支援は充足しているとして住民税所得割非課税世帯の高校就学に対する支援策を2025年度で廃止します。これは新年度に廃止した唯一の事業であり、問題です。
4.市民課窓口業務の民間委託
新年度予算では、市民課業務のうち電話対応を含め、戸籍以外の窓口業務を民間企業に委託しようとしています。繁忙期の待ち時間の短縮というなら、市民課経験者や全庁的な応援職員派遣、会計年度任用職員増員なども含め対応すればよいのではないでしょうか。
市民課には、吹田市の様々な制度を利用するにあたり必要となる住民登録をはじめ、すべての住民の個人情報が集積されています。入れ替わりの激しい民間事業者が取り扱うことへの住民の懸念が払しょくできないこと、11月末で15名の会計年度任用職員が雇い止めになる問題、仮に雇用が継続できても昇給分がリセットされる問題、直営と委託職員が関わることで1件当たりの処理時間が長くなること、偽装請負が起こる可能性ととなり合わせであること、中心的な業務ノウハウが市職員ではなく事業者に蓄積されることなど、公的責任を後退させる委託はやめるべきです。
5.障害者福祉年金・難病患者支援金の再構築
廃止の際に「サービス給付にあてる」とされていましたが、新年度の予算のうち、新規の障がい者サービスは、約7000万円しかない。障がい福祉年金として支給されていたのは年間約2億円で、再構築に同額があてられるべきところ実質は単なる廃止・削減となっている。生活そのものを支えるという目的にふさわしい再構築となるよう求めます。
6.福祉人材確保
市として独自の施策は、これまで通りのままであり、不十分です。高齢者・障がい福祉の計画推進にあたり事業者に行ったアンケートには「家賃補助や奨学金の返済補助」など、実質の賃金をアップさせる市の施策に期待するという意見が寄せられています。全職種より月に5万円低い収入の解消は報酬改定期に国に要望するだけでは解決しません。奨学金返済にもあてることができる、保育士サポート給付金のような具体策を早急に検討し予算化されるよう求めます。
7.吹田第三幼稚園と東保育園の統合
この間、地域の連合自治会・当該幼稚園の保護者や同地区の小学校のPTA・同地区内の私立幼稚園の保護者会・影響を受けると想定される地区の公立認定こども園のPTAから要望書が市と議会に提出されています。市の計画がいかに実情や地域の課題などと整合性がないことのあらわれであり、再検討されるよう強く求めます。
8.東西道路(市道片山町21号線及び朝日が丘町12号線)拡幅整備
東西道路東側、片山坂への合流部の、信号機設置の可否や、配置が現時点では不透明であり、車の流れや交通量予測を示したうえで、周辺道路や、住宅環境への安全対策も示すべきである。また今後、旧市民病院跡地購入事業者が敷地内に東西道路を整備する可能性があり、3.9億円の市費を投じて整備する必要性、緊急性が問われる。児童遊園の敷地を大幅に削ることを、当事者の子ども達、子育て世代の方たちに声を聞くことなく実施すること、影響の大きい山手町や出口町の声を聞かずに実施することは時期尚早といえ、再検討するべきです。
さて憲法第92条の規定により定められた地方自治法では、地方自治体の役割は「地域住民の福祉の増進」にあります。現在、数年間に及ぶコロナ禍からの立ち直りに冷や水をかぶせるように、長期にわたる物価高騰が中小業者の経営と市民生活を襲い、苦しめています。そのような社会状況のなかで本予算案が市民の願いにこたえたものになっているのかどうか、具体的に述べたとおりです。自治体としての本市の役割を果たすことがいっそう重要になっていると考えます。
本予算案にはこれまで市民が要望し、市の努力で前進した内容が多々含まれています。また具体的に指摘し、要望したように引き続きの取り組みと努力が求められる内容も数多くありました。市民と関係者の声を聞き、いっそうの努力を求めるものであります。
しかし問題点で述べたように不十分な物価高騰対策や、高等学校学習支援金の廃止、また個人情報保護の懸念などで過去に一度撤回した市民課窓口業務の民間委託、障がい者福祉年金廃止による不十分な再構築、さらに吹田第三幼稚園と東保育園の統合では多くの関係者から再検討を求められるなど、地方自治体の本旨を忘れたかのような市長の政治姿勢は重大であり、認められません。以上、問題の多い本予算案には賛成できません。 (賛成多数により可決)