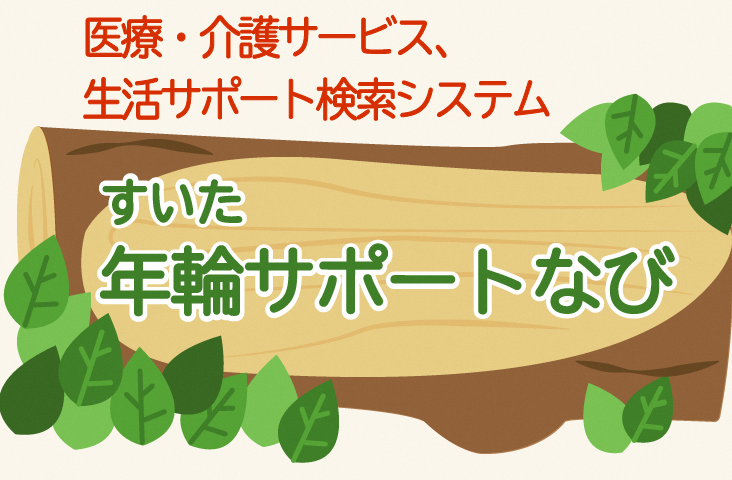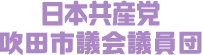■市民生活と新年度予算について
(問)本年1月、生鮮食品の消費者物価指数は前年同月比で21・9%増、コメは70%増となっている。物価上昇を反映し、真に生活が大変な人へ支援が届くように、市の各種制度を見直すことが必要。低所得者向けの事業の対象設定を緩やかにする必要がある。杉並区が就学援助の所得制限を生活保護基準の1・2倍から1・3倍に引き上げたように見直すことが必要ではないか。
(答:行政経営部長)制度の要件に所得階層に応じた線引きを設けている事業は多数ある。子育て関連政策などでは、所得制限自体を撤廃して負担制限を図っているものも一定ある。妥当な水準に設定をしており見直しは考えていない。
■吹田市地域合同防災訓練の在り方について
(問)自主防災組織の吹田市合同防災訓練の参加状況はどうなっているか。中には実践的でない状況も見受けられる。役所の中の意識や災害対応能力は日々進歩していますが、合同防災訓練についても次のステージに移るよう、地域の皆さんと在り方を検討していただきたいと思いますが、御所見を伺います。
(答:危機管理監)1月の合同防災訓練について、別の時期に実施された地域を除き6780名が参加、安否確認や避難訓練、本市との情報伝達訓練を実施した。地域独自の訓練も実施されているが、地域間で取り組みに格差もあったため、今年度は個別相談会を案内し、訓練メニュー一覧などを用いて相談に対応してきた。
(問)地域の合同防災訓練について。中には実践的でない状況も見受けられる。役所の中の意識や災害対応能力は日々進歩しているが、合同防災訓練についても次のステージに移るよう、地域の皆さんと在り方を検討していただきたい
(答:危機管理監)自主防災組織情報交換会は、活動発表会も含め3回開催し、延べ51団体、91名が参加した。
加えて、地域防災の核となる人材を確保するため、地域防災リーダーを広く募り、育成を進めている。その後も、活動発表会や各種防災イベントなど様々な情報を獲得できる場を案内している。今後とも、誰でも参加しやすいイベントも含め、最新の知識やスキルを得ることのできる場の提供を進めていく。
■埼玉県八潮市の道路陥没事故を受けて
(問)インフラの維持管理状況について、市民の不安の声にこたえていただきたい。
(答:下水道部長)予防保全の維持管理として、腐食の起こりやすい所について重点的に点検を行うなど、下水道管の重要度に応じて計画的に点検を行っている。異常が確認された場合は、自動式テレビカメラや目視により内部を詳細に調査し、破損等を特定する。修繕や下水道管を新しくする改築工事を行い、破損等による道路陥没の未然防止に努めている、
■戦後80年、被爆80年の取組について
(問)新年度は戦後80周年の事業を市民との連携も含めどのように進めるのか。
(答:市民部長)非核平和資料展を含む市民平和の集いをはじめ、市内大学生との連携など様々な取組を通じて、改めて平和の尊さやを考えていただく。
■障がい者福祉年金・難病患者給付金について
(問)昨年9月支給を最後に、障がい者福祉年金が廃止された。代わりに福祉サービスを充実するとしていたが、今回ほとんど提案されていないではないか。
(答:福祉部長)経済的負担軽減を目的に、排せつ管理支援用具の基準額見直しを行う。重度障がい者福祉タクシー料金助成の交付枚数の増加、リフト付タクシーの利用を通年実施、精神障がい者に対する居宅介護加算制度及び強度行動障がい者の受入れ加算の創設、障がい福祉の仕事の魅力発信、通学支援事業の制度化、手話講習会の拡充を提案している。
■教員の働き方改革について
(問)小学校教員の時間外勤務の理由は、授業準備が最も多い。新年度予算では、週15時間勤務の専科講師を6人配置しようとしているが少なすぎる。抜本増を求める。
(答:教育監)市費専科講師の配置については、授業準備に費やす時間の確保を目指す。今後、効果検証をしっかりと行い改革が一層進むよう努める。
■市民課の窓口業務委託について
(問)市民課業務の委託が提案をされたが3年前市が取り下げた経過があるが、今年12月から市民課窓口業務委託と、らくらく窓口証明書サービス等を実施し、来年6月からおくやみコーナーを導入するとしている。正規職員12名、会計年度任用職員15名を削減するとし、会計年度職員は雇い止めとなる。
郵送・窓口ともに、戸籍謄本や住民票、印鑑登録証明書を発行するため、事業者は、戸籍簿、住民基本台帳、印鑑登録原票を閲覧するが、親族、本籍、親族関係、婚姻、離婚、世帯構成、現住所や過去の住所、マイナンバー等、プライバシー性の高い情報が記載され、委託社員が扱うことを、市民は懸念している。既に委託している窓口業務の社員は何人入れ替わったか。
(答:市民部長)マイナンバーカード交付業務については、2月1日現在で37名おり、期間内に入った人数が17名、出た人数が14名となっている。
(答:福祉部長)介護保険事務は、37名中委託当初から引き続き従事している人数は13名となっている。
■市の政策決定と市民参画の在り方について
(問)後藤市政において、市民参画の形骸化が進んでいる。政策立案段階や政策決定する前に、当事者や関係者の意見を聴取
せず、市民に周知しない。突然議会に提案し、異論が出たら今後丁寧に説明していくと答えるなどがその例である。
山五小学校の統廃合、障がい者福祉年金・難病患者給付金の廃止、桃山公園のパークPFIなどが代表例である。実質的な市民参画を実現するため、市民への事前の情報公開、情報提供、情報共有を原則とすることを提案する。市長に問う。
(答:市長)提供することが可能な情報と、正当な手続きを経ていない段階での情報とを区別し、提供可能な情報については、その発信方法も考慮しつつ適切に公表する、それが民主的な市政の基本であると考えており、そのようにこれからも対応する。
(問)これからも、との答弁だがそうなっていない。
今議会に提案された「社会通念上相当な範囲を超えた言動による職員の被害の防止に関する条例」(いわゆるカスタマーハラスメント条例)との関係できく。「不当に市民の権利を侵害することのないよう、慎重に対応しなければならない」という原則は評価をする。しかし、当事者への説明を果たしていない場合もある。市民の意見に耳を傾け、市長が市民と共にどう市政運営をするか、セットで考えなければならない。
(答:市長)「市民の意見を聞く」というフレーズには様々な段階、種類がある。情報提供があり、質問が出てくる。それにに答える段階で理解をいただくのが行政の仕事です。全ての政策に賛否両論があり、だから議会がある。最終的な政策提案の責任は行政にあり、決定は議会にある。
※その他、給食費無償化の通年実施や片山町の東西道路等について取り上げました。
吹田の「今」を
お届けします