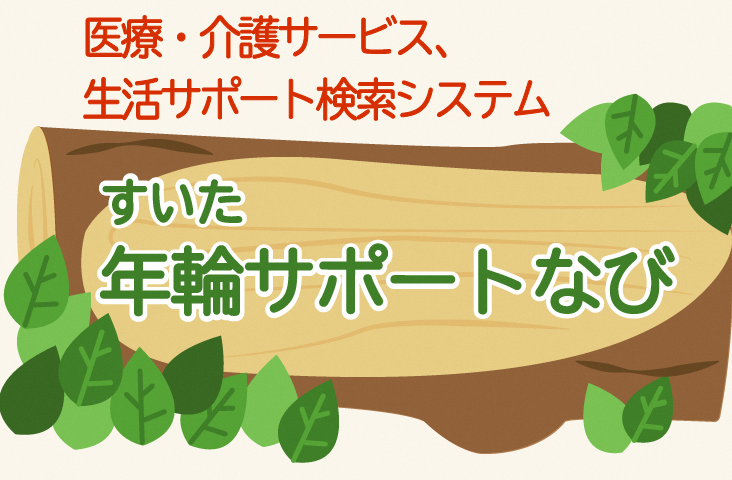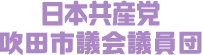11月議会初日に行われた2023年度決算認定に対して述べた、日本共産党の意見を紹介します。
評価できるもの
●パートナーシップ制度について
パートナーシップ制度がスタートし、23年度は7組の方々が申請され、大変喜ばれていることは評価できます。お金がかからず、みなさんに喜んでいただける制度です。これからも、市の姿勢を示し、ファミリーシップ制度への発展へとつなげていただくよう期待します。
●公益内部通報の制度について
吹田市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例で公益内部通報の制度などを定め、その受付や審査を内部組織である「コンプライアンス審査会」と「公正職務監察員」として弁護士による外部窓口の2つの組織を設置していることは評価できます。職員はもちろん、委託業務を行う職員等にも公益内部通報制度を周知し、通報者の保護に努められたい。過去10年間で公益内部通報は4件であり、この数は公正な職務遂行が行われていると見るべきか、その評価は定かではありませんが、日常的に違法・不当な行為を防止し、コンプライアンス意識のさらなる向上に努め、市民に信頼される公正な市政運営を推進してください。
●危機管理室の取り組みについて
相次ぐ災害により、市民や地域単位での防災意識は高まっています。新型コロナウイルス感染症の5類に移行後、地域での防災啓発活動や訓練、講座等の実施が増えており、危機管理室も共に取り組まれていることは評価できます。自主防災組織の立ち上げや活動に対し、より一層の支援を求めます。
●女性職員が働きやすい消防職場の環境整備について
施設の新築や改修に伴い、女性エリアの整備等、ハード面では整ってきています。一方、大多数が男性である職場において、女性職員が相談しやすい体制や女性隊員を増やすための取り組みが課題です。2024年から女性活躍推進担当として女性の管理職員を配置されたことは評価できます。しかし、まだ管理職としても女性は一人だけです。今後もジェンダーの視点で、研修及び職場の環境整備に努められたい。
●中学生の交通安全教室の授業について
始めたことは評価できます。各校区内で起こった事故や、ヘルメットをかぶらず事故にあった事例など具体的例を挙げ、リアルな表現、画像で行っており、交通ルールを守る大切さを実感できる内容であり、継続・拡充して頂きたい。
●上の川上部空間を活用したまちづくりについて
花壇踏切まで延伸できるか調査をし、大阪府と協議を重ねていることは評価できます。地域住民の長年の交通安全対策実施の願いに応えられることを期待します。
●マンション管理の適正化推進に関する条例について
届出登録をした管理組合等が、612/678、約95%まで進めてきた事は評価できます。管理不全に陥るマンションを残さないため、残り5%の実態把握に努める粘り強い取り組みと、それに必要な体制確保を進めていただきたい。
●デートDV予防講座について
全中学校での実施を目標として、当該年度は18校中14校の実施となっており同じテーマの授業を行っている学校が1校となっています。実施校は増えていますが、実施していない学校も残されており全中学校実施に向けた努力を求めます。また、小学校で行われていた「みんないきいきプログラム」を復活し、系統的に行うよう求めます。
●公共施設のトイレにおける生理用品の配備について
2024年2月から男女共同参画センターのトイレに置き始め、大量にとっていく人もなく実施状況は良好とのことです。他部局にも周知しており公共施設を持つ各所管での検討を求めます。
●小学校給食費の全額補助、中学校給食の半額補助について
通年実施していることは評価できます。今後も継続するよう求めます。
●学習支援教室について
2カ所増やされたことは評価できます。必要とされるこどもたちが、通うことができるよう、更なる充実を求めます。
●公立保育所の一時預かり事業について
新たな実施とともに、定員を増やしたことは評価できます。一時預かりのニーズは高く、また緊急一時保育もニーズが高いです。引き続き、子育て支援の充実のために、より進めていくように求めます。
●保育士サポート給付金について
保育士確保の具体策について、取り組みを実施されたことについては評価できます。条件や申請などを簡素化することや、5年目までとしていることについては今後、実施をしていく中で、より発展させていくことが必要です。具体的には確保とともに、継続して働くことができるように定着支援となるような施策についても、検討されるように求めます。
●妊産婦の包括支援と低所得妊婦への検診補助について
検診の補助については、対象は国の基準通りとなっています。中高生などハイリスクとされる若年者へ対象を広げることについて、市独自の努力が必要です。妊産婦への支援については、望まない妊娠や予期せぬ妊娠から中高生を守れるように、そして性被害から守るために、いのちの安全教育など、性教育について、教育委員会との連携や検討を始めたことは評価できます。具体化し、包括的な支援と吹田市独自の支援策が充実していくように求めます。
改善を求めるもの
●南山田市民ギャラリーについて
2021年度に、指定管理者の指定議案審議において、この施設の利用実態から、施設の必要性と活用方法について検討が必要であることを指摘しました。2023年度は310日の開館日のうち、展示等有償による利用は52日で、233日は指定管理者の自主事業として無償による展示を行っていたとのことであり、無理やり開館していた感が否めません。利用ニーズが低い施設を今後どうしていくのかが課題です。ただ、前回審議時の指摘を受け、今後の在り方検討を始められるよう動きだしたことには注目したいと思います。
●職員の時間外勤務について
働き方関連法に基づき、時間外勤務の上限を定める等、規則の改正や時差勤務、テレワークの導入など柔軟かつ多様な働き方により、この5年間でほとんどの職場において、1人当たりの時間外勤務時間は減少してきました。様々な取り組みを行いながら、業務量の多い職場については、職員の増員も含め適切な人員配置を求めます。
●市内の駐輪場の利用状況について
過去5年間、定期で100%の利用率を超えている所や、一時利用で再整備を進めている所と同程度の回転率になっている駐輪場についても、需要予測や整備計画の策定がされていません。利用率や、要望等を参考に、需要予測や整備計画の策定を進める事を求めます。
●児童センターの欠員について
欠員を補充することも必要ですが、1日に多いところでは1000人を超える来館者があります。また要配慮家庭やこどもたちへの対応など、日々、責任の重い仕事を行っているにも関わらず、配置はすべて会計年度任用職員でなおかつ欠員があり、補助員で業務が行われています。児童センターは児童福祉法に基づく、福祉施設です。責任をもって、現場で判断することができる正規職員の配置や、せめて責任者だけでも正規職員で配置し、専門職として業務を行えるよう、根本的な処遇改善することについて検討するよう求めます。
●生活福祉ケースワーカー
平均1人107ケースを担当することになっており、標準ケース数(80ケース)から27ケース超えている状態になっています。過去5年間も同様の状況が続いています。予算要求し、今年度は若干、職員が増えていますが、まだまだ追いついていません。コロナ禍や、複雑化する相談への対応など含め標準ケース数となるよう、任用資格の研修の保障や福祉職の採用を増やすなど努力を続けてください。
●学童保育の施設について
畳のささくれや、網戸、トイレが暗い・古い・臭い・男女共用等の諸課題、エアコンの能力不足や、手洗い場への通路や階段に屋根がないなど、施設改善の要望が多く出されています。また、扇風機などの備品が壊れているという声も多数寄せられています。年度をまたいで積み残しているものがあり、その原因は予算不足ではなく、対応する職員数や技術職員が配置されないなど、職員体制にあります。老朽化対応や、時代に合わないなどの施設の課題をいったんリセットするため、せめて時限的措置として職員を配置するなど、放課後の子どもの生活場所としてふさわしい、安全で快適な空間にするよう求めます。
問題点
●あいほうぷ吹田の指定管理について
指定管理者制度の導入により、受託者は介護報酬を受けて運営することになるとして、市の委託費を半減しました。障がい者事業所の介護報酬は、日額報酬のため、利用者数や通所日数に左右され収入が安定しません。介護報酬をあわせた収支に差異はないとはいえ、不安定なスタートであったのは市の公的責任の後退です。
●地域包括支援センターの人員配置と福祉人材確保について
1人増員すると予算化はされましたが、2つのセンターで人材が確保できず、1年間配置されないままです。増える相談に対応するとしていましたが、受託者まかせにせず、配置できるように市が責任をもつことが必要でありました。市もホームページでのせるなど、努力は認めますが、それだけでは確保できず、今後さらなる具体策が求められます。また市が基幹センターとして、専門職を配置し、役割を果たしていくのかが問われます。
今後は、福祉人材確保と合わせて、吹田市の福祉を支え、障がいのある方の日々の暮らしと、今後の高齢化社会を支えていく、福祉の担い手の確保について、その支援策について、実態に見合った策を具体化されるよう求めます。
●公園の魅力向上事業について
公園協議会の運営に関して、公園に対する様々な思いを持つ市民の間で、それらを取りまとめていく作業は難しい問題です。公園協議会の運営は指定管理者となりますが、指定管理者は駐車場や樹木の伐採等の管理等が前提で選定されており、市民の多様な意見を取りまとめることには熟達していないようです。
今後、指定者管理事業者を導入する際に、そういった適格性を見極めて事業者を選定していく必要が有ると考えます。
●公立保育園の民営化検証について
保護者へのアンケートが行われ、そのことについての報告はありますが、あくまで大人の視点の意見のみです。
検証委員会の意見でも出されていたように、保護者のアンケートの項目に、こどもからの聞き取りをしてもらうなど、こどもの影響調査の方法はあるはずです。また、こどもの様子の変化など、きちんと検証されるべきでした。民営化後の満足度調査をみると、公立保育園の課題があきらかになりました。しかし、どのように事業に活かすということが何も検証には書かれていません。今後に活かすならば、きちんと書かれるべきでした。
「建物は無償譲渡した」と報告がされていますが、自慢できるようなことではなく、経年劣化し譲渡後わずか3年で建て替えをするなどは本来の事業運営ならありえません。国庫補助があるとはいえ、修繕積立や建て替えのための自己資金の積み立てもできません。「衝撃もないのに劣化でガラスが割れる」「壁のボルトがおれて柵が落下する」など、日常ではありえないことがおこっており、こどもたちに怪我がないのが不思議なくらいです。それでも満足度を比較的保つ保育が行われています。本来であれば、瑕疵担保責任を市が負うべきものであったと思いますが、そのことについて何も触れられていません。
市にとっても、訴訟があり想定外の対応もありました。こども・保護者・市の職員・受ける事業者の負担など、もう少し掘り下げる検証が必要だと思います。
2012年に計画が決定し、計画の5園の民営化を完了するまでに12年です。その間に、待機児童が増え、2000人が入れないときがあり、アクションプランが策定され、施策を行っても、待機児童が減るものの、解消されない事態が続きました。2023年度の入所一次選考での入所不可数は700人、その後選考が行われ、発表数は0であったものの、隠れ待機児童は449名でした。年度のはじめに隠れ待機児童をつかんでいながら、対応策はとられるわけでもありませんでした。当初からわかっていたなら、年度途中で独自で待機児童数をつかむ努力が必要でした。
公立保育園を引き受ける事業者や担当の職員が、待機児童対策にならない民営化にその力を注ぐより、保育所に入りたくても入れない対策をとる方が建設的であったという、冷静な振り返りが必要であったと思います。そのことについても触れられていないのは残念です。
吹田市政の歴史の中で、事業そのものを民営化するというのははじめてのことで、どの市政の時に行ったのかというのは今後の吹田市の歴史でも記されていくことになります。その民営化の決断をした最高責任者である、後藤市長自身が心を寄せることもなく、なによりも「私は民営化を止めるやり方を知っている」と公言したにもかかわらず、多くの人たちの気持ちを踏みにじった、そのことこそ検証されるべきであり、それが全くないのは残念であるとしか言いようがありません。検証報告書に足りない部分について、追加で検証として残すことを求めます。
●会計年度任用職員について
学童指導員や学校看護師、手話通訳者など専門職や特別な技能を必要とする職種でありながら正規職員ではなく、会計年度任用職員として業務にあたっています。近年、人材の確保が困難なため、民間事業者への委託や派遣会社への依存が顕著です。その経費は市が直接運営や採用する場合に比べ高額です。人材確保の困難な理由は様々ありますが、その一つとして時給の低さがあります。会計年度任用職員制度は同一労働・同一賃金を目的としていますが、専門職であっても4年以降は昇級がなく、経験年数が評価されないことは問題です。また、昨年の人事院勧告は給与のプラス改定でしたが、会計年度任用職員については、遡及して支払われないことにより不利益を被ったことも問題です。職務の専門性や経験が評価される給与体系の見直しを求めます。
●「子どもたちの未来と平和を語る集い」の後援取り消しについて
市は、取り消し理由として「報告の際レジュメを添付しなかった」「署名を配布した」「内容が政治的」としています。終了後の報告に講師のレジュメを添付していなかったとのことですが、添付漏れを指摘し、提出をもとめればよかったにもかかわらずそれをしなかった市の対応は問題です。署名を配布したのではなく、チラシに掲載されているQRコードを読み込めば署名できるというだけで、そのチラシを配布したのも主催者ではありませんでした。その事実を知りながら、起案書を修正しておらず、改めて事実を把握し事実に沿った公文書に修正するよう求めます。
●万博関連について
2023年度から万博担当としてシティプロモーション推進室に職員を1名増員しています。加えて、総務部付け職員を研修名目で博覧会協会に2名派遣し、吹田市の人件費で万博準備業務を担っています。大阪府下では職員体制に余裕がないとして派遣していない自治体が15自治体あります。万博開催都市ではない吹田市で、ほかにも業務多忙な部署もある中、万博担当としてあえて1名増員する必要があったのか疑問です。
●二十歳を祝う式典の経費について
経費が昨年より約70万円上がり、保護者席の設置に伴うことが主な理由とのことでした。加えて2023年度は、およそ10分間の時間を費やして式典の最中に来賓紹介しました。なぜ来賓紹介をすることになったのか。その時間があれば従来通り教育長も20歳の若者へエールを送ることができたはずです。逆に来賓紹介をするのならデジタルサイネージの費用は必要ありませんでした。
また、市長の家族のお笑いコンビをゲストとして招くことを市長が決定し、経費が前年度比で90万円増加しています。公的行事に自分の家族をゲスト出演させることを自ら決定し市税が投入されるなど、市政の私物化にあたるのではないでしょうか。
政治家としての倫理上の問題、それを誰も止めなかった組織としての問題はないのでしょうか。仮に工事契約であれば、市長の家族の事業者に単独随意契約をすることは問題視されますが、今回のような式典のゲストであっても市民の厳しい目が向けられていると認識すべきです。
●山五小学校統廃合について
2023年11月議会に、山五小学校の廃止議案が出されました。3学期から山三小学校と山五小学校にそれぞれ学校問題解決支援員と講師の合計4人を配置し、統廃合に向けて進めるためとして補正予算が同時提案されていましたが、結局配置できず執行されませんでした。体調等を理由としていますが、議決から職員配置までは2週間程度しかなく十分な時間がありませんでした。廃校を1年3か月後に設定し急いだ結果、準備不足のまま進められたためです。これまでの学校統廃合の教訓はなんだったのでしょうか。保護者に対し議決後は1度しか説明会が開催されておらず、議決の前も後も、当事者、関係者への説明が不十分であり猛省を求めます。
●図書館の自由と郷土の歴史について
吹田市は3月、図書館ホームページの「郷土の歴史」コーナーにおいて、吹田事件が朝鮮戦争に反対するデモ隊への弾圧事件であったことを、吹田事件の紹介文から削除しました。しかし、騒擾罪を適用しようとして、警察が被告らに自白を強要し、大量却下された裁判の経過や、デモ参加者に暴行・脅迫の共同意思がないとして騒擾罪を無罪とした判決を見ても、弾圧事件であったことは明白です。図書館ホームページの限られたスペースにおいて、事件の本質を端的に表した「弾圧」という表現は適切なものでした。図書館の自由宣言では、「個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制したりはしない」と述べられています。ホームページの書き換え行為は、「図書館の自由」を侵すものと言わなければなりません。
また、判決ではデモ参加者が武装していたかどうかについても検証されましたが、裁判所は「全体として防衛的なもの」と否定しています。「武力衝突」という市の答弁は、判決を尊重しておらず、不適切な発言であり取り消すべきです。
以上、全体で見れば評価できる施策も実施されていますが、市政の私物化、福祉に関する取り組みの不十分な点、当事者の意見を十分に聞かない市政運営に問題があると考えます。
2023年度も、市民生活は更なる物価高騰や社会保障の削減などで厳しい状況となり、必要な施策に対して柔軟かつ積極的な財政出動が行われるべきでした。2022年度決算において、財政調整基金は143億361万9千円で、2023年度決算は145億6356万8千円となり、2億6千万円増加しています。財政調整基金は年度間の財源の不均衡を調整し、不測の事態に備えることが目的です。必要な時に予算に繰り入れ、市民生活を支え、市民の福祉向上のために活用することが必要だと考えます。
地方自治の本旨である、地域住民が地域のことを決めるという住民自治を尊重するとともに、一段と厳しくなっている暮らしを守る防波堤の役割を果たすことを求め、2023年度吹田市一般会計決算についての反対意見といたします。
(賛成多数で承認、日本共産党は反対)