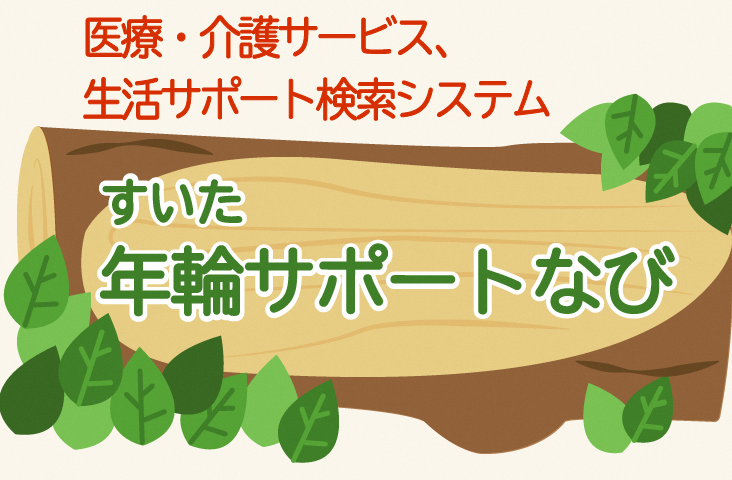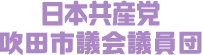*留守家庭児童育成室条例の一部改正に対する反対意見の内容を紹介します。
1997年6月に「児童福祉法等の一部改正に関する法律」が成立し、学童保育がはじめて法制化されました。1998年4月より学童保育は児童福祉法と社会福祉事業法に位置づく事業とされ、 学童保育は、「放課後児童健全育成事業」という名称で、「国と地方自治体が児童の育成に責任を負う」というものです。児童福祉法第6条の3第2項は「保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るもの」としています。
学童保育の目的・役割 は、共働き・一人親の小学生の放課後(土曜日、春・夏・冬休み等の学校休業中は1日)の生活を継続的に保障することを通して、親の仕事と子育ての両立支援を保障することです。ということから考えても、まず市が行うべきは「学校施設の一部を使用した事業」という位置づけについて、法律に基づき見直すことが必要ではないでしょうか。
値上げの理由として、「事務量が増えている」としその内容は、コンビニ決済の導入・人材派遣による人材確保・民間委託などのために、人を増やしたといわれていましたが、サービスに直接かかわるものではありません。また、民間委託を拡大してきたことにより、委託料そのものが増えていることも大きな要因となっています。機械的に『使用料』に反映させるものではないと思います。
市は「受益者負担率の基本は50%だが37・5%にし抑えている』としていますが、もともと2019年までは『公共性が高い、福祉』として25%の受益者負担率でした。児童福祉法に基づく事業で、なぜ公共性が高いと判断をされないのか、疑問です。また、今のままの方針で『使用料』として、機械的な見直しを行っていくと、単なる値上げを繰り返していくことにしかならず、いまのままの位置づけだと、4年後には9000円ぐらいへの引き上げが想定され、事業の目的から遠ざかるようなことを繰り返していくことになります。延長保育料についても同様です。 延長保育も利用すると、保育料と合わせて、月2500円の引き上げとなり、年間で30000円の引き上げです。全体では1億3200万円の負担増になります。利用している保護者の方が「待機をださないために足りなくなっている先生たちを増やし、正規職員にするとか安定して働きつづけられるようにすること、そしてずっと要望している施設の改善が劇的に進むなら理解できるけれど、家計の状況も知ることもなく、値上げになるのは厳しいなと思う」これだけの利用者世帯の負担を増やすにもかかわらず、世帯の収入状況調査も行われていないのは残念としかいえません。
吹田市では、働き続けたい母親が、こどもたちを何とかして放課後を安全にいきいきと生活させたいという思いで1965年に高野台で共同保育がスタートしました。1982年には、他市に先駆けて条例化され、1986年にはすべての公立小学校内(当時は37校)に設置され、吹田市のどこに住んでいても、校区の小学校内にある学童保育に入室できるようになりました。
また障害のあるこどもの入室も積極的にすすめられ、他市では受け入れられていなかった、府立支援学校の障害のあるこどもたちも居住する地域の学童保育に入室でき、療育システムの充実のもとで、発達指導員による巡回相談などの専門的な支援体制も構築されてきたということをふりかえってみても、極めて公共性の高い福祉の事業だといえるとおもいます。この点を踏まえ、いまの事業の位置づけ、そのものの見直しをおこなうことを求めるとともに、子育て世帯の負担が重く増えることになる、条例改正については反対といたします。
(賛成多数で可決、日本共産党は反対)