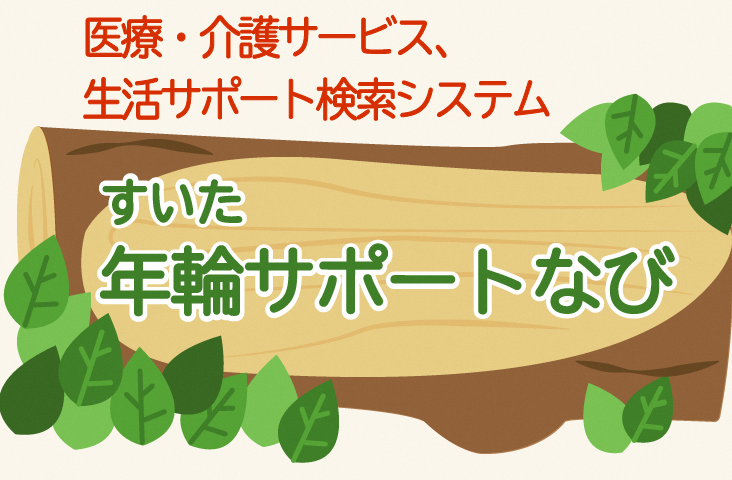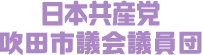※12月20日、11月議会最終日に討論採決が行われた一般会計補正予算案(賛成多数で可決)についての日本共産党議員団の賛成意見を紹介します。
予算案のなかには、2028年度内に民設民営のセンター方式で、中学校の全員給食を実施するための予算が計上されており、全員で食べる中学校給食の実施は、長年、保護者や市民が強く望んできたものです。
【これまでの経過】
2000年初頭、全国的には約8割で実施されている中学校給食が大阪ではわずか1割程度、全国ワースト1の実施率でした。吹田市では、市民の願いで1996年、センター方式が中心であった小学校給食が全て自校方式に切り替わり、今度は中学校給食を実現させたいとの思いが高まっていきました。
2004年には、「小・中学校給食検討会議」が設けられ、2009年から3年かけて全ての中学校で選択制デリバリー方式の給食を開始。しかし、「冷たくておいしくない」、「配膳室まで取りに行くのが面倒」など、喫食率は10~13%程度で推移しました。
保護者や市民は、「選択制では食育もできない」、「全員で食べる温かい、美味しい中学校給食を」と、署名活動に取り組まれ、市や議会に届けられました。
2019年、後藤市長が2期目の選挙公約に全員で食べる中学校給食の実施を掲げ、2020年に「中学校給食在り方検討会議」を開催。「美味しく楽しく食べられる食育の推進ができるシステムの確立」や「生徒全員が同じメニューを食べる機会の提供」などの考え方がまとめられました。その後、2021年4月から教育委員会に全員喫食の中学校給食実施などを担当する「教育未来創生室」が設置され、2026年度の実施や建都イノベーションパークに摂津市との共同運用で大規模給食センターを「民設民営」で実施する方針が示されました。結局、摂津市との合意はならず、今回の単独民設民営方式となりました。わが会派としては、保護者や市民と共に求めてきた中学校給食の形とは大きく違っています。
わが会派は、この間、他市の実施事例の視察や給食の学習会などを重ね、自校方式や親子方式での実施を具体的に提案し、早期実施を求めてきました。しかし、市は「喫食率の引き上げに努力する」との一点張りで、長い間、引き伸ばしてきました。また、「在り方検討会議」後もセンター方式ありきで検討が進められました。もっと早く、デリバリー方式に見切りをつけて検討に着手していれば、自校方式や親子方式で実施できたところもあったのではないか、センター方式であっても直営で実施できたのではないか、非常に残念です。
【民設民営方式で行うことの問題点】
全国的にもまだ2つの自治体でしか実施事例のない、民設民営方式は、本当に子どもたちに安全で安定的に給食が提供できるのか、懸念が払拭されたわけではありません。
わが会派は、公設民営のセンター方式で実施している自治体での状況をお聞きしましたが、重大事態には至らなくても、思いがけない事態は結構ありました。
例えば、「異物が付着していたために、その日のささみチーズフライが欠品になり、副食がスープだけになった」、「肉団子入りのシチューで、全員に肉団子が当たらなかった」、「隣の学校はマグロの角煮が一人5、6個あったのに、うちの学校は一人2個しかなかった」、「食缶を開けたら、スパゲッティが少な過ぎて、全員に配食できなかった」「味が薄いと思ったら、煮すぎて汁がなくなり、水道水で薄めていた」、「麻婆ナスの調理をするのに、フライする釜と炒める釜の位置が悪く、炒められずあえるだけになった」など、異物混入や数の数え間違い、量が少ないなど、学校現場が振り回されている事例。また味が落ちた、品数が少ない、デザートが減ったなど、子どもたちからの声もありました。
【これらを踏まえての要望】
●大規模な調理には、想定できない事態が起こります。大規模調理の実績がある事業者を選定すると言いますが、本当に安全に適切にできる事業者があるのか。見極めが必要です。先ほど紹介したようなリアルな状況をセンター方式で実施している他市の事例を聴き取り、研究し、想定しない事態が起こらない対応を要求水準書で求めてください。
●食材の選定と購入、献立作成は市が行うとしていますが、食材の検収及び調理は事業者が行います。検収や調理は一般の調理業務とは異なる専門性が求められます。適切に行われているか、定期巡回だけではなく、抜き打ちも含め市がいつでも施設内に立ち入ることができる契約内容にしてください。
●給食の調理業務は特殊な調理設備で行います。作業工程を円滑にする設備の配置、作業を指揮する能力と調理員の適切な配置が必要になります。吹田市の場合のように2パターンの献立を3品調理するとなると、設備の配置は十分な検討を重ねなければなりません。事業者の提案頼みではなく、他市の事例も参考に市も関わって整備してください。
●吹田の小学校給食は、今まで一度も食中毒など重大事案を起こさず、安全で美味しい給食を提供してきました。市の実施する衛生研修や調理実習などに事業者の職員も参加できるようにするなど、吹田市の給食の良さを理解し、共により良い給食を進めていけるような仕組みを検討してください。
●こどもたちへの食育については、加配の栄養教諭が必ず配置されるよう府に求め、「給食は教育の一環である」とする憲法や学校給食法、食育基本法の目的が達成できるよう努めてください。
●安全な給食提供のため、民間事業所の職員がモチベーションを持ち、安定的に業務に従事できることが重要です。賃金等処遇が適正に図られる委託料になるようにしてください。
【今後も公的責任でより良い中学校給食の在り方を求めていく】
学校給食はこどもたちの楽しみです。その一食でもミスがあれば、いのちを奪うことにもなりかねません。給食の実施責任者は吹田市です。今後も保護者とこどもたち、市民のみなさんと一緒により良い給食になるよう、市の努力を求め続けていきます。