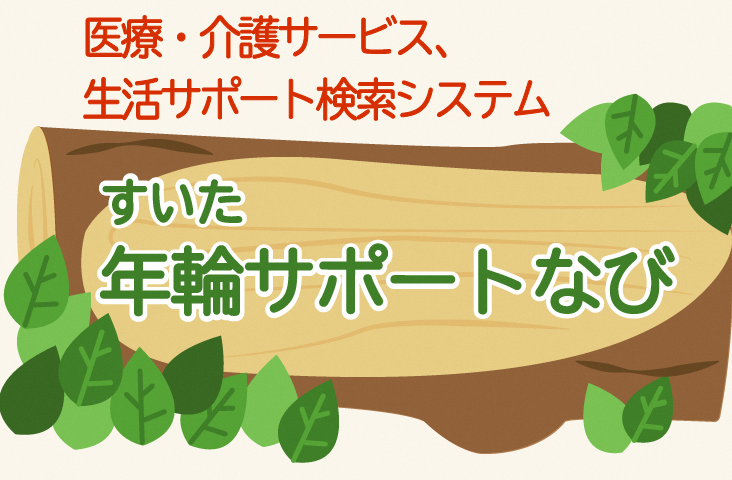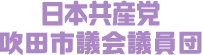■使用料・手数料及び自己負担金設定に関する基本方針は見直しを求める
(問)今議会に文化・スポーツ施設等使用料と学童保育料の改定が提案された。維新市政時代、「行政の維新プロジェクト」により、施設使用料等の値上げと減免制度の縮小が進められた。後藤市政になっても値上げ志向には変わりはない。公共の施設は市民の福祉増進を図るもの、受益者負担率等、基本方針は見直しが必要である。
(答:行政経営部長)施設使用料に係る受益者負担率は原則50%を市負担、施設の目的等を勘案し負担率を設定。受益と負担の公平性を確保し、コストが下がれば値下げする。基本方針における算定方法は妥当と考える。
(問)学童保育料は現行料金の1.5倍、2千円の値上げ、年間にすると2万4千円の負担増になる。学童保育は就労保障であり、子育て支援事業である。物価高騰の下で、大きな負担増。せめて保育料同様に第2子は無償等、軽減策は検討しなかったのか。
(答:地域教育部長)持続可能な事業運営を図るため、様々な取り組みをした結果、一人あたりの経費が増加している。受益者負担率を子育て支援施策の観点から37・5%を維持し、上限を抑制している。
■介護人材の確保について
(問)介護職の給与は全産業平均給与より約7万円低い。現場は離職する人も多く、介護サービスの提供ができなくなる。東京世田谷区では高齢者・障害者施設に対し、人材確保や処遇改善、経営のために使える「緊急安定経営事業者支援給付金」の支給を、千葉県の流山市は介護福祉士と介護支援専門員の資格を持つ正規職員に月9千円の賃金補助を行っている。吹田市でも直接的な処遇改善支援をすべきではないか。
(答:福祉部長)介護人材確保は喫緊の課題と認識している。障害福祉分野では強度行動障害を有する方の年齢が20歳代、40歳代に多く、若年層の人材確保が課題である。奨学金返還の支援を含め、効果的な人材確保策を重層的に実施できるよう検討する。
■手話言語等促進条例の施策推進方針について
(問)手話言語等促進条例の施策推進方針について、寄せられたパブリックコメントの主な内容と件数について聞く。
(答:福祉部長)118通259件。主な内容は、市報すいた等での啓発、小中学校で手話に接する機会、手話に関するイベントの実施、手話通訳派遣の範囲を広げる、医療機関や公共施設に手話通訳を配置等であった。
(問)取り組み状況を年1回、社会福祉審議会障害者施策推進審議会に報告するが、当事者の意見を反映させて、着実に施策を推進すべき。
(答:福祉部長)社会福祉審議会の障害者施策推進専門部会の作業部会で取り組みの推進にあたっても意見をいただきながら、着実な施策の推進を進める。
(問)手話言語条例が制定されたことを広く市民に周知せよ。
(答:福祉部長)施策推進方針のやさしい日本語版を作成したいと考えている。来年は市報で特集記事を考えている。パンフレットや動画の作成等、あらゆる手段を活用し、手話言語の理解促進に取り組む。
■災害時要援護者支援について
(問)災害時要援護者登録及び個別支援計画の進捗状況と業務上の課題について聞く。
(答:福祉部長)2023年度末時点で約1万4千人が要援護者名簿に登録。その内、821件の個別避難計画を提出いただいた。本年11月には、浸水リスクの高い地域の登録者5千2百人に個別避難計画作成を勧奨した。課題は避難先の選定や避難支援者の確保など作成が困難な人がいること。
※その他、医療的ケア者や強度行動障害、難病患者等、災害時要援護者の支援について質問しました。
■中学校給食について
(問)民設民営で実施するための事業者選定に関わる予算及び今年度から15年間の給食調理等業務に係る経費について債務負担行為が提案された。懸念事項について聞く。
民設民営の場合の栄養士の配置、事業者側の栄養士、献立作成会議及びメニューの作成、検収や調理作業についての市の確認方法、調理員の配置人数や必要な調理設備、調理に要する時間と学校に配送される時間の設定、選定委員会の外部有識者について、選定委員に保護者や栄養士を入れない理由等について聞く。
(答:学校教育部長)民設民営方式は府費による栄養教諭定数は0人。加配により配置されるよう府に要望する。事業者の栄養士は、一定規模の給食施設の経験を有する者を求める。献立作成委員会は既存の組織を活用する。メニューについては、学校の栄養教諭や市の栄養士のワーキングチームで検討する。検収や調理作業は定期的な実地での検査も含め検討している。人員体制や調理設備は事業者募集時に本市が示す要求水準をもとに、事業者が提案する。調理に要する時間や学校へ配送する時間は「学校給食衛生管理基準」、「大量調理施設マニュアル」に沿って事業者が設定、提案する。選定委員会の外部有識者は、給食を通じた食育に関する知見を有する大学教授などを想定している。市の栄養士は推進会議やワーキングチームで意見を聴取している。保護者や学校関係者を選定委員会の構成員としては考えていない。
■小学校給食費の無償化について
(問)9月議会で「小学校給食費について、2024年10月以降の半年間も無償化を継続するよう求める決議」が可決したが、学校教育部は無償化の継続はしない旨の回答をした。政府が11月22日、新たな経済対策として「重点支援交付金」の増額を閣議決定し、小中学校の給食費の活用も可能としている。物価高騰が続く中、給食費無償化を実施せよ。
(答:市長)物価高騰は落ち着きつつある。小学校の給食費は保護者負担とさせていただく。
■大阪・関西万博の遠足について
(問)9月議会では、本市教育委員会から大阪府教育庁に対し、児童生徒招待事業に対する安全対策等の回答がなく、参加の可否については判断できない。情報収集に努め適切に判断すると、教育監、教育長、市長が同様の見解を示された。その後の状況を聞く。
(答:教育監)その後も質問に対する明確な回答はなく、安全確保がされていないため、対応を保留している。
(問)万博は来年4月13日の開催。学校現場は、年度末に向けて卒業式や入学・進級の準備、教職員の体制等、非常に忙しい時期を迎える。早期に参加をしない判断をすべき。
(答:教育長)来年度の授業計画の検討をする時期を視野に入れながら判断する。
(答:市長)授業計画の時期に判断する。おそらく12月中。
■万博記念公園駅前周辺地区活性化事業計画について
(問)10月28日付で、市長から知事に対し、「関係法令に適合した事業となることを求める文書」を発出。その後、事業者は、条例で建築物の制限を定める地区内の共同住宅計画を一旦除外し、次期以降に予定していた万博外周の外にある敷地の共同住宅建設を1期プロジェクトに前倒しをするとした。事業者は、共同住宅に代わる代替案を示さないまま、この12月にも開発及び環境アセスメント等、行政手続きを進めるとしている。アリーナと一体の開発事業であった。変更ではなく、白紙に戻して見直すべきではないのか。
(答:市長)地区内の共同住宅を除外した計画で開発の手続きをすることは可能である。地域住民に対しては、変更した計画を丁寧に説明することを求めている。ただ計画が確定した場合、一体事業として、再度、構想手続きから行うことになる。環境アセスも同様である。