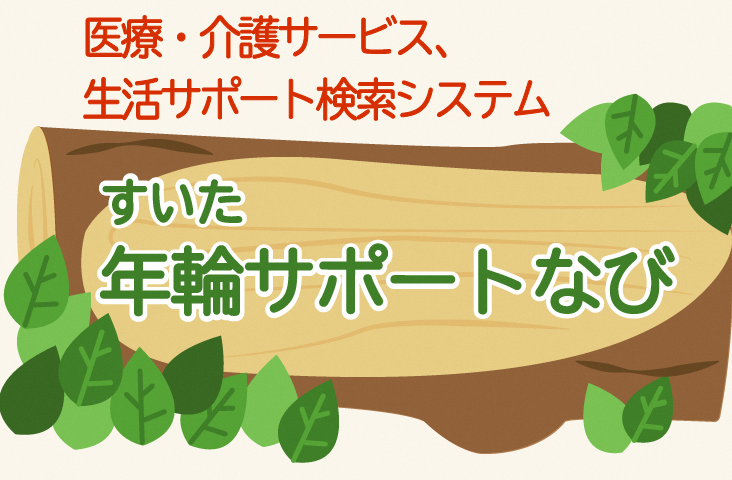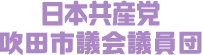10月29日に行われた決算常任委員会での日本共産党の討論内容についてお伝えします。
■障害者福祉年金事業廃止について
廃止財源活用について、条例廃止の提案時には廃止財源の使い道は示さず、後に「現金給付からサービス給付の充実」の方針が示されました。しかし、障害のある人が障害のない人と同じように当たり前に生活するためのサービス、つまり支援は市として当然やるべき事業であり、年金廃止財源はあくまで障害者の経済的支援として再構築するべきです。しかし、そうはなっておらず、障害者の生活のわずかな足しであり、ささやかな楽しみを奪っただけの結果になっています。
■学校規模適正化について
学校規模適正化計画は過大校対策が主たる目的として示されました。しかし、最優先課題であった千二・千三・豊一小学校等の適正化計画は白紙になり、過少校である山五小学校の廃校が優先的に進められました。廃校の賛否にかかわらず、時間をかけて議論、準備をしてほしいと願う保護者の声には応えず、わずか1年余りで廃校が決定しました。子どもたちへの影響を考え、子どもたちの気持ちに寄り添い、丁寧に進めるために学校問題解決支援員を配置するとしていましたが、結局市費では、支援員は配置されず事務職員のみの配置に留まりました。
また、子どもたちにとっては、山五小最後の一年間であるにもかかわらず、「組織マネジメント力を有する管理職を配置する計画」などという教育委員会の事情で、廃校に至るまで、こどもたちの気持ちを受け止めてきた校長を異動させたことは、おおよそ子どもたちに寄り添った対応とは言えません。
市長も廃校について、「子どもたちの意見を聞く」と発言されていましたが、子どもたちの声を聞く場は、結局一度も設けられませんでした。その理由を子どもたらの求めがなかったからと答弁されましたが、子どもたちに責任転嫁する姿勢は市長としていかがなものか。市民の信頼を損ねます。深く反省していただきたいと思います。
■奨学基金の廃止について
奨学基金廃止に至る経過について、 奨学金基金は高等学校等学習支援金制度として充てられてきました。またこの制度の廃止については当事者に知らされることなく提案されました。基金の残高3200万円の使途については、教員の働き方改革や不登校対策予算に活用するよう検討を行ったとのことですが、そもそもの制度創設のきっかけとなった低所得世帯の高校生を支援したいとする寄付者の遺志や趣旨とは異なるものです。現在も物価高騰が続く中、経済的な困難を抱える家庭の子どもたちが希望を持って高校生活が送れる制度は残すべきでした。
■物価高騰による市民生活への支援について
実質賃金が3年連続マイナスに加え、物価高騰により市民生活が厳しい中、2024年度実施の物価高騰対策は、小学校給食全額補助が半年間、中学校給食半額補助、福祉施設等への応援金支給、低所得者支援金給付に留まっています。吹田市には市民生活を支える役割が求められましたが、幅広い市民への支援策は実施されませんでした。2024年度の一般会計は、国の交付金の減少や物価高騰による負担増、人件費や扶助費の増加などがあり、実質収支の黒字化を図るため、財政調整基金から19億円の繰り入れが行われました。しかし、決算後も約129億円の残高があり、小学校給食全額補助の半年延長や中小業者及び全市民対象の支援策を積極的に実施すべきだったと考えます。
以上、全体で見れば市民にとって必要な施策も行われていますが、市民福祉の向上や生活支援の取り組みが不十分であること、子どもたちをはじめ当事者の意見をきかない市政運営に問題があることから、本決算に反対します。
*日本共産党と市民と歩む議員の会が反対しましたが、賛成多数で認定。
なお、決算全体の意見は、11月定例会初日の本会議で述べました。