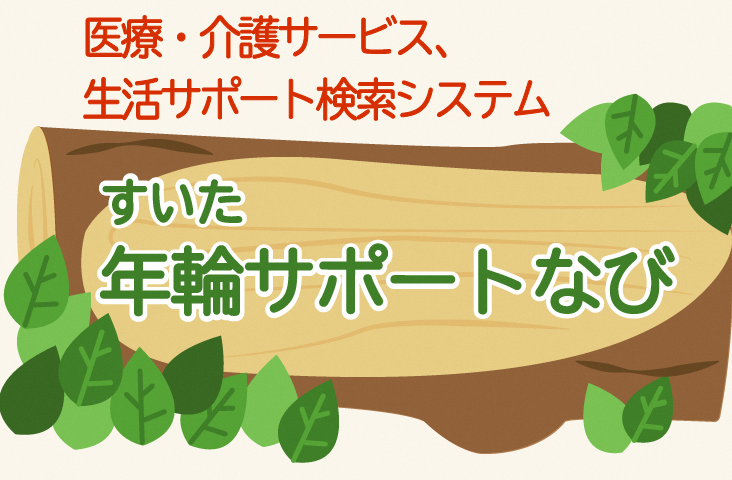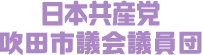■保育園でのネズミ発生時の市の対応を問う
問)2023年10月から、施設管理等が委託となった保育園で、ネズミが発生した際の対応について問う。
ネズミが保育園の給食室内で発見され、対策工事の依頼から工事施工まで約5か月もかかったのは何故か。
(答:学校教育部長)先行他市でも、包括管理業務委託の導入当初数年間は混乱がある。混乱を避けるため、学校管理下で、業務の承認を行った。学校管理下と、修繕事業者の繁忙により、想定以上の日数を要した。
(問)包括管理事業者が修繕施工事業者に見積りを依頼してから見積書が到着するまで約1か月、包括管理事業者から学校管理課へ見積りを提出し、修繕施工の承認依頼をしてから修繕の承認が下りるまで約1か月半、包括管理事業者から施工業者へ実施依頼をしてから施工実施までが2か月弱を要している。包括管理事業者が間に入ったことで工程が増え、時間がかかったのではないか。
(答:学校教育部長)本市で初めての取組であり、発注までに時間を要することもあったが、現在は包括管理事業者に情報やノウハウが蓄積され、迅速化を図っている。
(問)保育現場の関係者は、放置されているように感じたようだ。依頼から施工実施までの約5か月間、保育現場の関係者にはどのような状況説明があったのか。
(答:学校教育部長)事業者から保育現場への状況説明はできておらず、進捗状況の共有に課題があった。今後は一定のめどを定め、遅れる場合には連絡するなど、各施設が状況を把握できるよう取り組む。
■必要な人に支援が届く体制の整備を
(問)支援が必要な方を、生活再建や支援へとつなげるため、令和7年度から重層的支援体制整備事業が開始される。縦割り行政の弊害を破り、複雑な問題を抱えた人を、包括的に伴走型で支えられるよう期待する。縦割りの最大の原因は何で、重層的支援体制が実施をされれば、どのように解決が図られるのか。
(答:福祉部長)個人の情報共有や支援方針の検討等を関係者間で共有するため、会議の構成員に守秘義務を課す法定の支援会議と、本人同意の上で実施する重層的支援会議が新たに規定された。庁内関係部局や外部支援機関等が、分野を超えスムーズな連携や情報の共有を図る仕組みができ、課題の解決を目指すことができる。
(問)住宅確保要配慮者の支援機関である、吹田市居住支援協議会の予算と体制の強化を求める。業務が事務局のみなと寮に集中をしている。要支援者の掘り起こしの必要もあり、人員の増員が必要と考えるがどうか。
(答:都市計画部長)ノウハウの蓄積がなく、事務局に負担が集中し、効果的な支援につながらない課題がある。今後、居住支援団体・不動産関係団体とのスムーズな連携のため、体系的な支援体制の確立や強化と、人員の増員について検討する。
(問)国交省からの助成金は、年々大幅に減少しており、協議会の存続が大変になっている。補助を実施すべきと考えるがいかがか。
(答:都市計画部長)協議会の活動は、全て国庫補助金を基に運営されているが、必要経費を大きく下回っており、安定した資金の確保が課題だ。協議会の運営に対する資金的なサポートについても検討が必要と認識している。