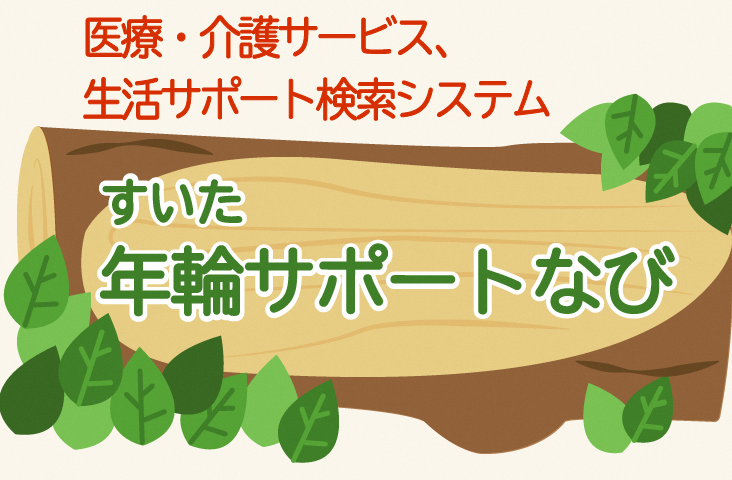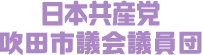■障害者の収入は貧困ライン 障害者福祉年金は必要な支援
(問)全国の共同作業所の連絡会であるきょうされんが2023年5月~2024年4月に実施した「障害のある人の地域生活実態調査」によると、障害基礎年金等、年額収入が相対的貧困とされる127万円の貧困ラインを下回る人が全体の78・6%という結果だった。
調査結果から吹田市の障害者福祉年金は役割を終えるどころか求められている支援であり、経済的支援は必要がある。所見を聞く。
(答:福祉部長)今後、障害者福祉サービスの充実を図るため、障害当事者等の意見等も踏まえ、必要なサービスを必要なときに利用できる環境の構築に取り組む。
■暮らしの場について
(問)障害者の経済的自立の困難は、家族に依存する状況に追い込んでいる。調査結果では、障害者の49・0%は親と同居、50代前半でも3割が同居、老障介護の実態が浮き彫りになっている。
強度行動障害など重度障害の暮らしの場が全く足りていない。障害支援区分5、6の重度障害の人を受け入れているグループホームは何か所あるのか聞く。
(答:福祉部長)本市が支給決定している障害支援区分が5または6の人を受け入れているグループホームは、本年7月末現在、市内32か所のうち17か所である。
(問)もともとグループホームは重度の方を受け入れる制度設計になっていない。全国のグループホームで区分6の利用者は1割にも満たないことを厚労省も認めている。吹田は事業所と現場の職員の努力で成り立っていると言える。重度障害に対応できる職員配置等、豊かなくらしを支え、安定的な運営と受け入れ推進するために、運営補助の増額が必要である。副市長に所見を聞く。
(答:福祉部長)グループホームにおける重度障害者の受け入れを促進するため、本年度から、障害者グループホーム運営事業補助制度に、施設整備にかかる補助を追加した。効果検証を行い、事業者ニーズの把握に努め、より効果のある制度の構築について引き続き検討する。
■障害福祉サービス等の報酬改定の影響について
(問)今年度実施された障害福祉サービス等の報酬改定は、基本報酬の減額、成果主義の強化、時間単価の導入など福祉事業の実態に合っていない。報酬改定後の障害福祉事業所の状況について聞く。
(答:福祉部長)福報酬改定の影響については、7月のサービス提供分の請求額は、報酬改定前の3月サービス提供分に比べ11・2%の増となっているが、日中活動事業所へのアンケートや意見交換の場において、加算ありきの報酬となったことで人件費や家賃等の固定管理費の支払いが安定しないこと、開所時間の延長や加算取得のための事務負担増を職員の人件費等に還元しているため、事業者としての利益が増えている状況ではないと聞いている。引き続き、報酬改定の影響を注視するとともに、事業者の状況把握に努める。
(要望)実態は事業運営は非常に苦しくなっている。市としても現場の実情を国にあげ、報酬の再改定を求めよ。
■手話言語等促進条例制定後の市の施策について
(問)手話通訳者登録制度の創設が必要である。情報が伝わりにくいろう者にとって、特に災害時の不安は大きく、手話のできる支援者が求められる。
手話通訳者の登録が多ければ、災害時、条件のある登録者にろう者の安否確認や避難所等での支援が可能になる。手話通訳者登録制度の創設と災害時の支援について、所見を聞く。
(答:福祉部長)他市で実施されている手話通訳者登録制度の必要性は、障害当事者からも要望がある。
特に災害時においては、手話による意思疎通支援が必要な聴覚障害のある方にとって、手話通訳者による支援は不安を少しでも解消するために重要であると認識している。他市の状況も把握しながら、本市にとって必要な制度のあり方について検討する。
(問)手話通訳者の育成のため、ステップアップ講座などの実施が必要。所見を聞く。
(答:福祉部長)現在の手話講習会は、手話ボランティアの養成をめざすものであり、手話通訳者の育成に向け、よりレベルの高い市民向け講座の実施は必要であると認識している。今後、手話通訳に関する資格取得のためのスキルが身に着くよう、講座内容の充実に努める。
■医療的ケアを必要とする児童生徒に対応する看護師について
(問)派遣看護師に多額の経費がかかる。市の看護師確保のため、給与等処遇改善など効果的な対策について教育長に聞く。
(答:教育長)医療的ケア看護師を安定的に配置することが第一である。持続可能で適切な支援体制の構築に努める。