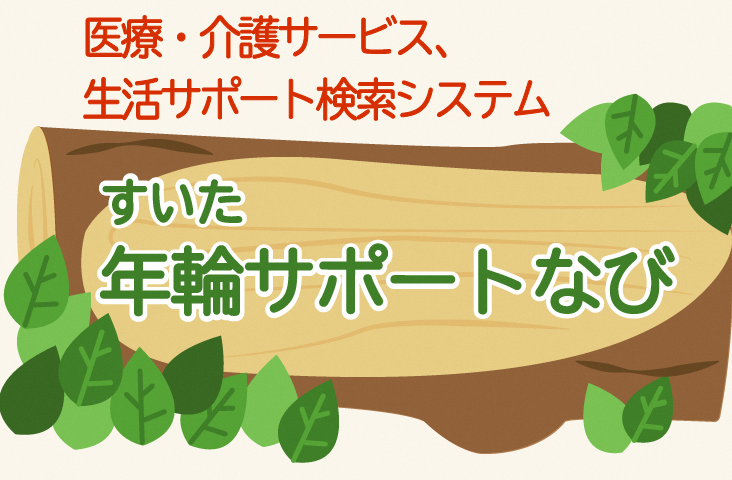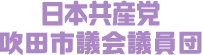2024年9月定例会の竹村博之議員の代表質問
問)教育委員会の「全員給食に向けた基本計画」にある、長期的な安定供給や経費面などを総合的に判断し、建都イノベーションパークでの民設民営によるセンター方式とした根拠。事業者の選定について、手法、評価基準、選定体制。リスク対応について市職員が現場でチェックできないことで、想定外の事態に至る可能性を否定できない。学校給食の安全面と安定性にとって、民設民営は問題が多い。
(答:学校教育部長)センター方式で調理の拠点を集約することで、将来の調理人材不足へ対応し、長期にわたり事業者を確保できると考える。選定はプロポーザル方式、体制は部長級職員で国立循環器病研究センターや公認会計士など外部の有識者からも意見を聞く予定。
■給食費無償化について
(問)物価高騰、主食であるお米も値上がりしている。全国で学校給食費無償化が広がっている。市は学校給食法を理由としているが、憲法26条と法に照らし、国も自治体の判断を認めている。年度途中で打ち切るのは考え直すべき。物価高騰に対する認識が市民の実感とずれている。
(答:市長)国による物価高騰対策の実施や物価の上昇傾向が緩やかになり、特段の事情が解消されつつあり、原則に基づき保護者負担とする。国策により方向性を示すべき。
■教員の長時間勤務の解消について
(問)長時間勤務の実態。業務に見合った人員の確保の取組み。教職員団体の勤務実態の調査では、クラスの人数がより少なくなることで全ての業務が軽減され、勤務時間が減少、多忙化の解消につながることを確認している。小中学校の早期の少人数学級、支援学級の児童・生徒にダブルカウント実施。ICTの導入で業務量が増加しているとの声がある。過度な学力競争につながる国や府の学力テスト調査をやめるなど検討すべき。
(答:教育監)重点課題と認識。本年度モデル実施として、教頭の長時間勤務の是正と教員の人材育成を図るため3校に学校副管理者を配置、中学校の部活動について5校5部活に平日及び休日の指導を外部委託している。昨年度実施した教員対象のアンケートを参考に、教員が本来業務である児童・生徒に向き合える時間を確保するため年度内めどに教員の働き方改革におけるグランドデザインを策定する。
■大阪・関西万博の学校単位の校外学習について
(問)5月定例会の代表質問で市長は「校長も意向調査に対応できるだけの情報を持てる立場にない中で、参加の意向を回答せざるを得ない行政手続きには重大な瑕疵を感じる。教育委員会にも責任がある」と答弁した。その後の教育委員会の対応。9月に万博協会が「防災実施計画」を発表したが、実効性が疑わしく不安が増している。本市教育委員会の自主性を発揮し、保護者や教職員の納得と理解を得られない校外学習は中止すべき。
(答:教育長)7月に大阪府教育庁に対して懸念される課題として約40項目の質問、8月に回答を受けたが約9割が未定・検討中という状況。懸念される課題が解消されない場合、実施の可否について適切に判断する。
(答:市長)心配する保護者の理解を得た上で、学校現場としても安全性を確認して、責任をもって参加の可否を判断するにはあまりにも不十分。
■万博アリーナ建設について
(問)北部大阪都市計画特別用途地区を対象にした、大阪府の万博記念公園駅前周辺地区活性化事業の事業予定者による提案内容について、2021年5月定例会と2024年5月定例会において住宅建設に反対する決議が採択され、市長に対して、例外規定の適用について慎重な判断を求めた。市が8月に提出した大阪府当初予算に対する意見・要望の中で「現時点において当該事業の構想は特別用途地区における当該条例に規定する要件を満たしておらず、法令に適合していないと考える」とある。市民が納得できる結論を求める。
(答:市長)構想は共同住宅を含む内容であり、条例ただし書きの適用による建築許可を前提としたものであり、共同住宅が必要な明確な理由、共同住宅を活用した取組の効果や実現性、継続性、その担保の方法が示されておらず、現時点で法令に適合していないと判断している。市として事業内容の再検討を強く求めている。
■国民健康保険について
(問)国の法改定で保険証が廃止される。保険証とひもづけされたマイナ保険証の取得状況。マイナ保険証を持たない、持つことができない方、あるいは持ちたくない方に不利益が生じないようにどう対応するのか。またマイナ保険証の読取り機のない医療機関を受診した場合の対応。
(答:健康医療部長)マイナ保険証の取得状況は、6月末現在、加入者数約5万8千人中約3万1千人で取得率約53%。被保険者証の新規発行終了となる12月2日以降、マイナ保険証を持っていない方には「資格確認証」を交付する。読取り機のない医療機関では、マイナ保険証を持つ方に送る「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを提示していただく。
(意見)保険証を廃止しても同様のものを配布する。市民に不安と混乱をもたらすだけの意味不明な施策。市民に対し正確な情報提供と丁寧な対応を要望する。
■子宮頸がんワクチンについて
(問)2025年3月末で、子宮頸がんワクチンのキャッチアップ接種の公費無料接種が終了予定。現在の取組状況、接種率の推移。副反応についての正確な情報提供、被害者に対する補償と支援、治療体制の整備。対象者への案内、検診の充実など早期発見が重要。対象者以外の接種費用は1回約3万円と全3回で高額。制度の延長など引き続きの取組みが求められる。
(答:健康医療部長)キャッチアップ接種対象者は、1997年度生まれから2007年度生まれの未接種の女性。70%から80%あった接種率は、対象世代で9%から30%。引き続き国の動向を注視していく。
■市民が憩える公園について
(問)桃山公園と江坂公園で、2022年7月からパークPFI及び指定管理者制度のよる管理運営が始まった。江坂公園は収益施設としてレストラン、カフェなど営業。公園唯一の土の広場(つどいの広場)では、年間通じてイベントが行なわれ、5月連休は有料の大型遊具が広場を占有、8月は有料プール、屋台が営業。子どもたちが自由に遊ぶ貴重な空間を奪っており、制度による弊害。他の公園にも制度を拡大する方針だが、江坂公園の実態、市民とりわけ子どもたちの声をよく聴き検証すべき。
(答:土木部長)パークPFI制度は、民間事業者のノウハウや資金を活用し効率化や再整備コストの縮減、長期的な視点を持った取組みが実現できる。公園利用者の声を聴くとともに、公園協議会で意見交換しながら多世代が様々活動できる場にする。
(意見)具体的に指摘し改善を求めたが、まともな答弁はない。地域の子どもたちの貴重な遊びをしっかりと維持すべき。引き続き求めていく。